野球観戦をより熱くする「登場曲」の魅力に迫る!その起源から進化、そして未来へ
野球観戦を彩る欠かせない要素の一つに、選手の「登場曲(Walk-up Song)」があります。選手が打席やマウンドに向かう際に流れるこの音楽は、単なるBGM以上の意味を持ち、選手の個性やアイデンティティを表現し、ファンとの一体感を高める重要な役割を担っています。
今回は、この登場曲がどのように生まれ、どのようにして現代のスポーツ文化に深く浸透していったのか、その歴史と魅力に迫ります。
アメリカにおける登場曲の夜明け:オルガン奏者の偉業
登場曲のルーツは、1970年代のアメリカ・メジャーリーグに遡ります。この文化の生みの親とされているのは、シカゴ・ホワイトソックスの専属オルガン奏者、ナンシー・ファウストさんです。
彼女がコミスキー・パークで、初めて選手に合わせた音楽を演奏したのが始まりと言われています。
- ファウストさんは、各選手の性格や状況に応じてユニークな選曲でファンを楽しませました。例えば、ハロルド・ベイン選手には「He’s So Shy」、ディック・アレン選手がホームランを打った際には「Jesus Christ」といった曲を演奏したそうです。
- 彼女はファンのフィードバックを選曲に反映させ、1973年にはオルガンの設置場所が観客席の近くに移ったことで、より試合の流れに合わせた即興演奏が可能になりました。
- 特に有名なのは、1977年に彼女が始めた、相手投手が交代する際に流す「ナ・ナ・ヘイ・ヘイ・キス・ヒム・グッバイ」という曲です。これはファンも大合唱し、「煽り曲」の原点になったと言われています。
- ファウストさんは41年間オルガン奏者を務め、出産による5試合を除いて休まずに職務を全うした「スーパーウーマン」としてその功績が称えられています。
生演奏から録音、そして選手の個性の表現へ
1990年代に入ると、球場での音楽はオルガンの生演奏から録音された楽曲へと移行していきます。
- 当初はボーカルが入っていないインストゥルメンタル曲が主流でしたが、次第に選手自身が「この曲を使いたい」とリクエストするようになり、個人がテーマ曲を選ぶスタイルが確立されていきました。それまでは球団やスタッフが主導して曲を決めていたのです。
- この転換を象徴する出来事が、1995年、ニューヨーク・ヤンキースのスーパースター、デレク・ジーター選手が自身の初打席でモンテル・ジョーダンの「This Is How We Do It」をリクエストしたことでした。
- 彼の行動は全国放送で広まり、選手自身が音楽で個性やアイデンティティを表現する文化が定着する大きなきっかけとなりました。
- 現在では、メジャーリーグの公式サイトが公式に登場曲リストを公開するほど、登場曲は野球文化に深く浸透しています。
日本プロ野球における登場曲の導入と進化
日本プロ野球における登場曲の導入は、アメリカよりやや遅れ、1990年代前半から始まったとされています。
- 日本でも当初は球団スタッフが選曲していましたが、1994年頃からは選手自身がリクエストするスタイルが広まり始めました。
- チームとして初めて全選手に異なる登場曲を設定したのは、1994年のオリックス・ブルーウェーブと言われています。
- また、個人としては、同時期に阪神タイガースの外野手だった亀山努選手が自らの登場曲をリクエストしたのが最初期の例とされています。
- その後、日本でも登場曲は徐々に普及し、1998年頃にはすべての球団が採用するまでになりました。これにより、選手は音楽を通じて自身の個性を際立たせ、ファンもその演出を楽しむようになりました。
野球だけじゃない!他競技における「入場曲」の概念
登場曲(Walk-up Song)の概念は、野球に限らず、格闘技やプロレスの世界でも古くから存在します。これらの競技では「入場曲(Entrance Song)」と呼ばれることが多いです。
- プロレス: 1941年にはゴージャス・ジョージがポンプ・アンド・サーカムスタンスを堂々と使用して登場し、「テーマ曲=キャラクター」という概念を確立していたと言われています。日本においても、1974年に来日したビッグ・バン・ベイダー選手が「Jesus Christ」をかけて花道を歩き、会場を騒然とさせました。さらに、1976年〜1977年にはミル・マスカラス選手が「スカイハイ」、そして何と言っても1977年の**アントニオ猪木選手による「炎のファイター」**で、入場曲の文化は完全に定着したと言えるでしょう。
- ボクシング: 1990年代初頭にはマイク・タイソン選手がレッドマンの「Time 4 Sum Aksion」を入場曲に使用し、大きな話題を呼びました。現代でも、ボクシングの井上尚弥選手がキルビルのテーマやドラマ「GOOD LUCK!!」で有名な「Departure」を使用するなど、入場曲は選手にとって不可欠な要素となっています。
現代における登場曲の役割と最新トレンド
現代においても登場曲は、選手にとってアイデンティティを示す重要な要素として定着しています。
- メジャーリーグでは、マリアノ・リベラ選手の「Enter Sandman」やエドウィン・ディアス選手の「Narco」のように、「この曲といえばこの選手」という形で選手のブランディング効果も生まれています。
- 日本でも、各選手がこだわりの曲を選んで試合を盛り上げています。選手によっては、打席ごとに曲を変えたり、チャンスの場面で特定の曲をリクエストしたりする人もいます。
- 球場の一体感を高める要素としても重要で、アメリカでは「Baby Shark」や「Whisper」のように観客を巻き込む演出も人気です。
- 一方で、野球の試合進行のスピードアップ化に伴い、登場曲の長さは短くなる傾向にあります。メジャーリーグではピッチクロック導入により、打者の平均登場曲の長さが14秒から9秒に短縮されたと言われています。
- NPBでは、近年TikTokで流行した曲やアニメのオープニングソングを登場曲に使う選手の割合が急上昇しています。
- また、選手によっては、調子が悪い時に気分転換のために曲を変えるといったルーティンの一環として登場曲を活用するケースもあります。長年同じ曲を使い続ける選手もいれば、定期的に曲を変える選手もいて、それぞれにこだわりが見られます。
登場曲がスポーツ観戦にもたらす魅力
ナンシー・ファウストさんから始まった登場曲の文化は、今や選手個人の象徴であり、スポーツ観戦の魅力を高める不可欠な要素となっています。音楽を通じて選手とファンの距離が縮まり、球場の一体感を生み出す登場曲は、今後もスポーツエンターテイメントにおいて重要な役割を担い続けるでしょう。
あなたなら、どんな曲を登場曲に選びますか?
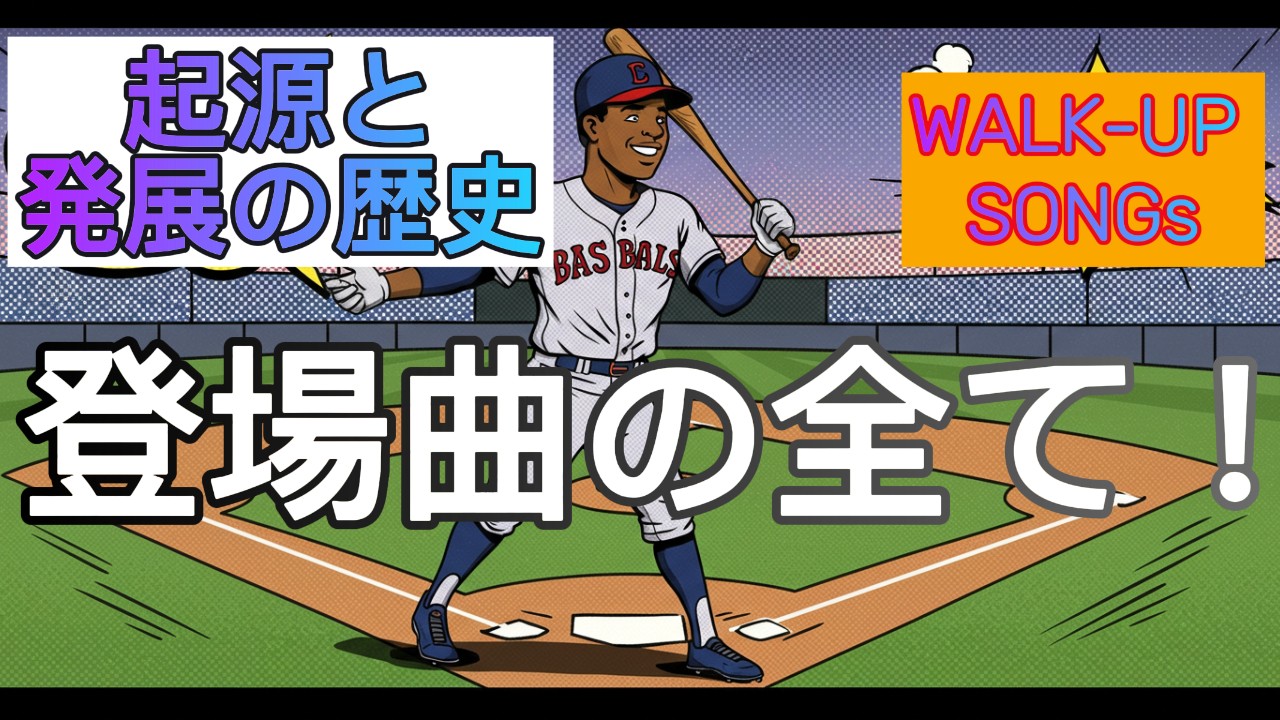
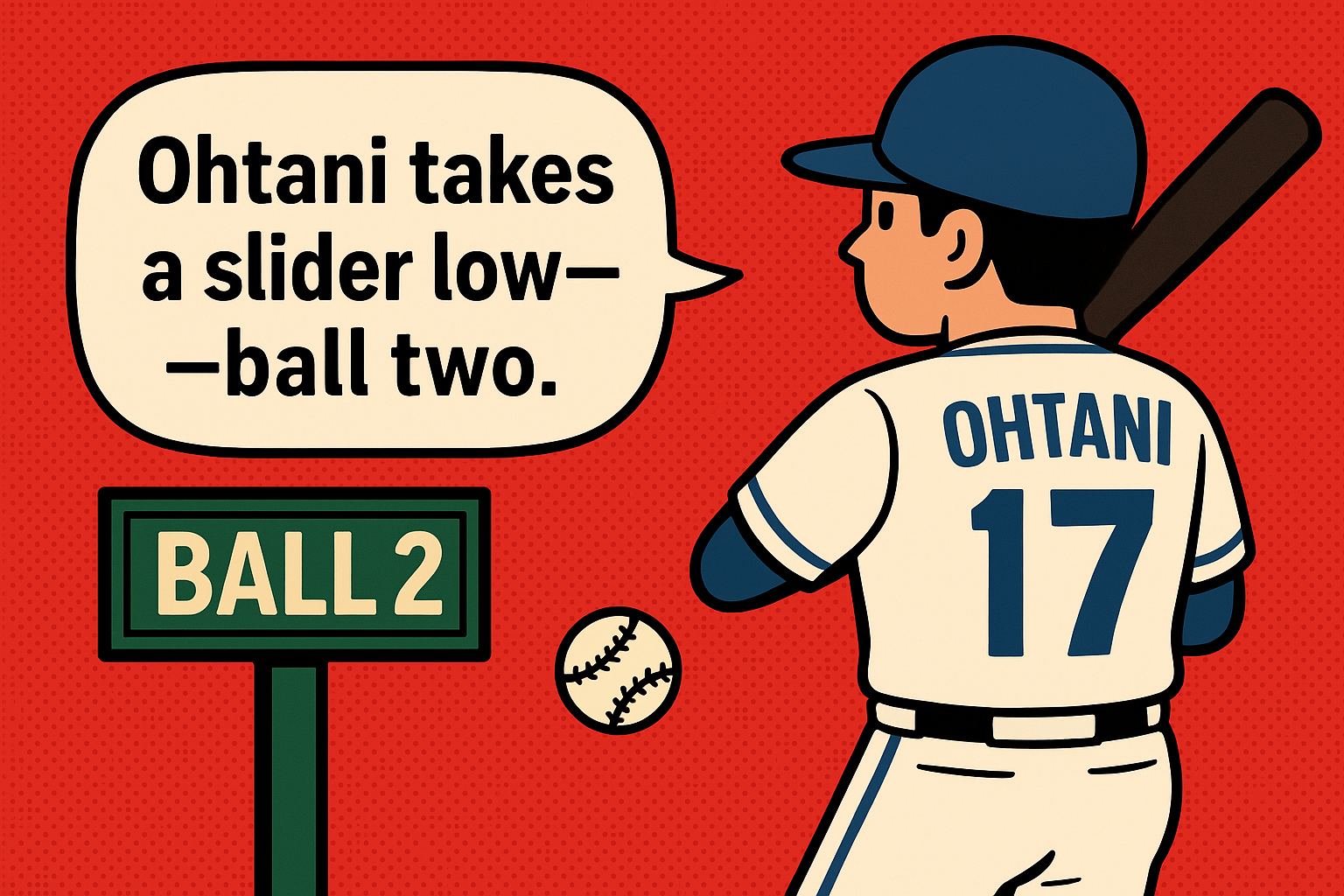
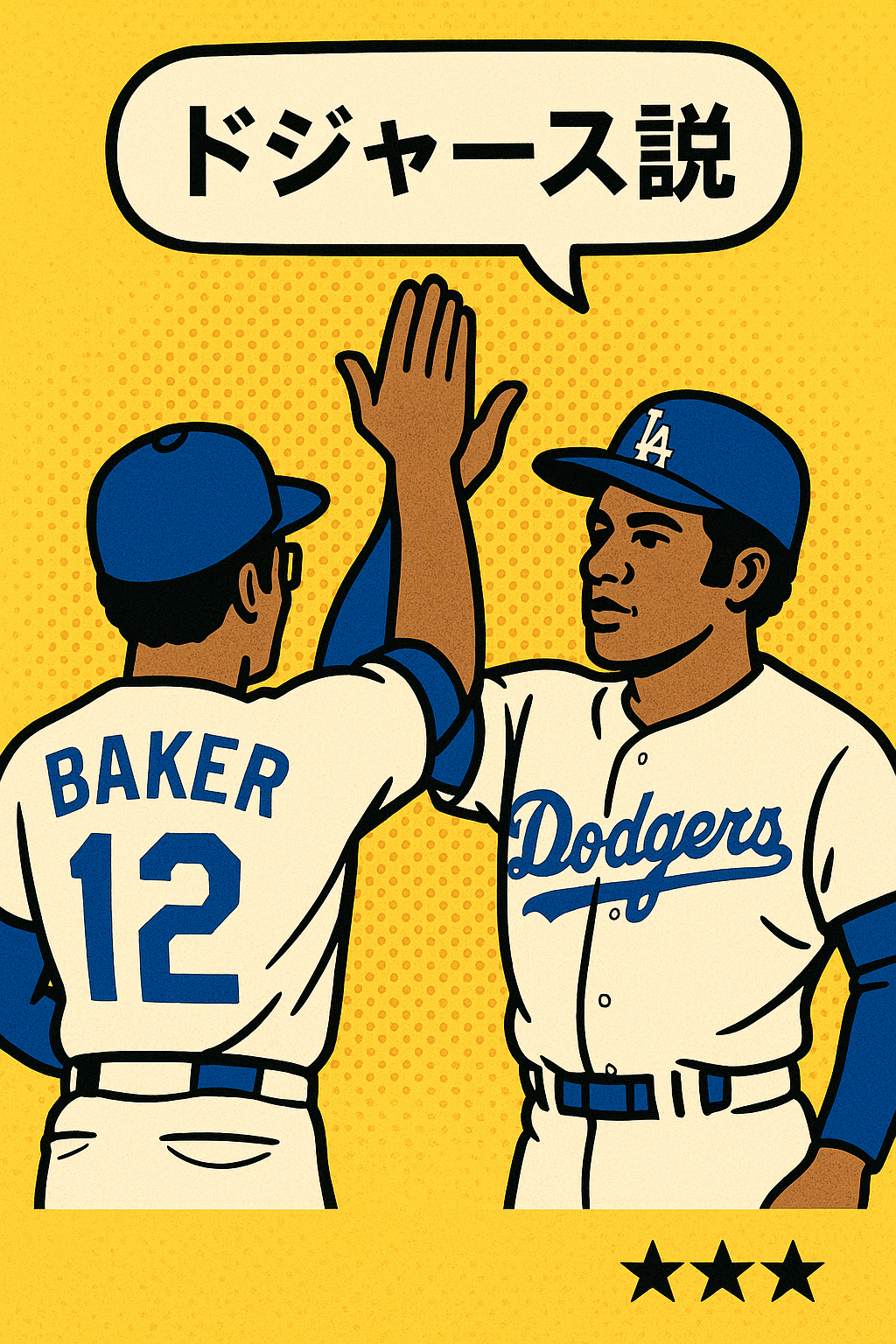
コメント